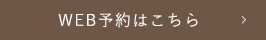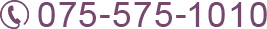皆様こんにちは、まきこクリニック院長の船越です。
秋から冬にかけて気温が下がり、空気が乾燥してくると、私たちの体にはさまざまな影響が出やすくなります。特に胃腸は外気の変化や生活習慣の影響を受けやすく、体調不良の原因となることが少なくありません。
寒さによる血流低下、冷たい飲食物の摂取、体の冷えや運動不足などが重なることで、胃腸のトラブルが起きやすくなります。本日のコラムでは、「寒くなってきた時期に気を付けるべき胃腸のトラブル」について解説いたします。
■寒さと胃腸の関係
寒くなると体は体温を保つために血液を体の中心部に集め、手足など末端部の血流が減少します。このとき、胃腸の血流も低下しやすく、消化機能が落ちることがあります。血流が滞ることで、食べ物を効率よく消化・吸収する働きが低下し、胃もたれや下痢、便秘などのトラブルを引き起こすことがあるほか、寒さによる自律神経の乱れも胃腸症状に影響します。
寒さで交感神経が優位になると胃腸の蠕動運動が低下し、消化不良や便秘が起こりやすくなります。冬は温かい飲食物を好む傾向がある一方で、冷たい飲み物やアイス、冷たい麺類などを夏の習慣のまま摂取してしまうと胃腸に負担をかけ、冷たい飲食物は胃腸の血流をさらに低下させるため消化機能を弱める原因となります。
■寒くなる時期に多い胃腸のトラブル
寒い季節に特に注意すべき胃腸の症状には、以下のようなものがあります。
1. 胃もたれ・消化不良
寒さによる血流低下や自律神経の乱れ、食生活の偏りが原因で、胃の消化機能が低下すると、胃もたれや食後の不快感が生じます。脂っこい食事や量の多い食事、夜遅くの食事も症状を悪化させやすく、胸やけや膨満感を感じることがあります。
2. 便秘
寒さによって体が冷えると腸の蠕動運動が低下し、便が腸内に留まりやすくなります。また、水分摂取量が減ることも便秘の原因です。寒い時期は暖房で室内が乾燥しやすく、体内の水分が不足しやすいため、便が硬くなりやすくなります。便秘が続くと腹部膨満感や食欲不振、肌荒れ、疲労感の原因にもなります。
3. 下痢
寒さや冷たい飲食物、ストレス、暴飲暴食などが原因で下痢が起こることがあります。特に外食、消化に負担のかかる食材の摂取、季節性のウイルス感染なども下痢の原因となります。寒い季節に起こる下痢は体力を消耗しやすく、放置すると脱水や栄養不足につながることがあるため注意が必要です。
4. 胃痛・腹痛
胃や腸の血流が低下した状態で刺激物や脂質の多い食事を摂ると、胃痛や腹痛が起こりやすくなります。胃炎や十二指腸潰瘍などの既往がある方は、寒くなる時期に症状が悪化することがあります。胃痛や腹痛が続く場合は、自己判断で市販薬に頼るのではなく、医療機関で相談することが重要です。
■胃腸トラブルの主な原因
寒い季節に胃腸の不調が起きやすい原因は、いくつかの要因が重なって起こります。
まず、寒さによって末端の血流が減少すると、胃腸の消化機能も低下しやすくなります。血流が滞ることで、食べ物の消化や栄養吸収がスムーズに行われず、胃もたれや腹部の不快感が生じやすくなります。次に、寒暖差や日照時間の減少によって自律神経のバランスが崩れることも影響します。
交感神経と副交感神経の働きが乱れると、胃腸の蠕動運動が低下し、便秘や消化不良を引き起こすことがあります。さらに、夏の習慣のまま冷たい飲み物を摂り続けたり、脂質や糖分の多い食事を偏って摂ったりすることも胃腸への負担となります。加えて、年末に向けて忙しくなる時期には、睡眠不足や過度のストレスにより胃腸の働きがさらに低下し、不調が悪化しやすくなります。
これらの要因が組み合わさることで、寒い季節は胃腸の不調が起こりやすくなると言われています。
■胃腸トラブルを防ぐ食事の工夫
寒くなってきた時期は、胃腸に負担をかけない食事を心がけることが大切です。
〇温かい食事を意識する
スープやお粥、煮物など、温かく消化にやさしい食事を中心にすると胃腸の血流が保たれ、消化機能を助けます。また、冷たい飲み物やアイスの摂取は控えめにし、白湯や温かいお茶を取り入れることが効果的です。
〇消化にやさしい食品を選ぶ
脂肪分や香辛料の多い食品は消化に負担をかけやすいため、寒い時期は白身魚、鶏ささみ、豆腐、野菜の煮物などを積極的に取り入れましょう。
〇食物繊維を意識する
便秘対策として野菜や海藻、きのこなどの食物繊維をバランス良く摂ることが重要です。食物繊維は腸内環境を整え、便通改善に役立ちます。
〇発酵食品で腸内環境を整える
ヨーグルト、納豆、味噌などの発酵食品は、腸内細菌のバランスを整え、免疫力を維持する助けになります。
〇適切な水分補給
寒い時期は喉の渇きを感じにくいため、水分摂取が不足しやすく、便が硬くなりやすいです。お茶や白湯、スープなどをこまめに摂ることが大切です。
■生活習慣のポイント
食事だけでなく、日常生活における工夫も胃腸トラブルの予防には非常に有効です。
まず、十分な睡眠を確保することが大切です。体は睡眠中に修復され、ホルモンバランスも整うため、毎日7〜8時間の質の高い睡眠を心がけることで、胃腸の健康を保つ助けになります。次に、適度な運動も効果的です。ウォーキングやストレッチなど軽い運動を行うことで血流が促進され、消化機能の改善につながります。また、腸の蠕動運動が活発になることで、便秘や胃もたれの予防にもなります。
さらに、体を冷やさない工夫も重要です。寒暖差に対応できる服装を選んだり、温かい飲み物を摂取したりすることで体を冷やさず、特に腹部を温めることは胃腸の働きを助ける効果があります。そして、ストレスの管理も忘れてはいけません。自律神経の乱れは胃腸症状を悪化させる原因となるため、入浴や趣味の時間を持つ、深呼吸を行うなど、日常的にリラックスできる時間を意識的に確保することが大切です。これらの生活習慣の工夫を組み合わせることで、寒い季節でも胃腸の健康を守り、トラブルの予防につなげることができます。
■注意が必要な胃腸症状
寒くなる時期に起こる胃腸トラブルは多くの場合軽症ですが、以下の症状がある場合は早めに医療機関で相談することが大切です。
・強い腹痛や持続する胃痛
・黒色便や血便
・激しい下痢や嘔吐、脱水症状
・食欲不振が数日間以上続く
・体重減少や倦怠感が改善しない
これらの症状は胃潰瘍、十二指腸潰瘍、感染性胃腸炎、炎症性腸疾患など、重篤な病気が隠れている可能性があります。自己判断にて我慢することなくお早めにご相談ください。
■当院の内視鏡検査の特徴
つらくない胃カメラ•大腸カメラ検査を、みんなが気軽に受けられる社会へ
◎生活習慣病から消化器疾患まで幅広く対応
◎地域に根付いた胃腸のかかりつけ医
◎複数名医師体制による安心の診断
◎女性医師による苦痛の少ない内視鏡検査
◎消化器内視鏡専門医による苦痛の少ない検査
◎眠ったまま出来る無痛胃カメラ・大腸カメラ検査
◎土曜・日曜の内視鏡検査
◎ハイエンドの検査機器完備
■まとめ
寒い季節は、気温の低下や寒暖差、生活リズムの乱れなどにより、胃腸にさまざまな負担がかかりやすくなります。その結果、胃もたれや消化不良、便秘、下痢、腹痛などのトラブルが起こりやすくなります。原因としては、血流の低下や自律神経の乱れ、冷たい飲食物や偏った食生活、ストレスの影響などが挙げられます。
予防のためには、温かく消化にやさしい食事を中心に、食物繊維や発酵食品を取り入れ、こまめな水分補給を心がけることが大切です。また、十分な睡眠、適度な運動、体を冷やさない工夫、ストレス管理など、生活習慣全体を整えることも胃腸の健康維持に重要です。寒い季節だからこそ、食事と生活習慣の両面から胃腸をいたわり、体調不良を予防することを意識しましょう。
当院では、鎮静剤の使用や経鼻内視鏡によって、楽に内視鏡検査を受けていただける体制を整えております。些細な胃腸症状でもお気軽にご相談ください。
〒601-1431
京都市伏見区石田大受町32-2
まきこ胃と大腸の消化器・内視鏡クリニック